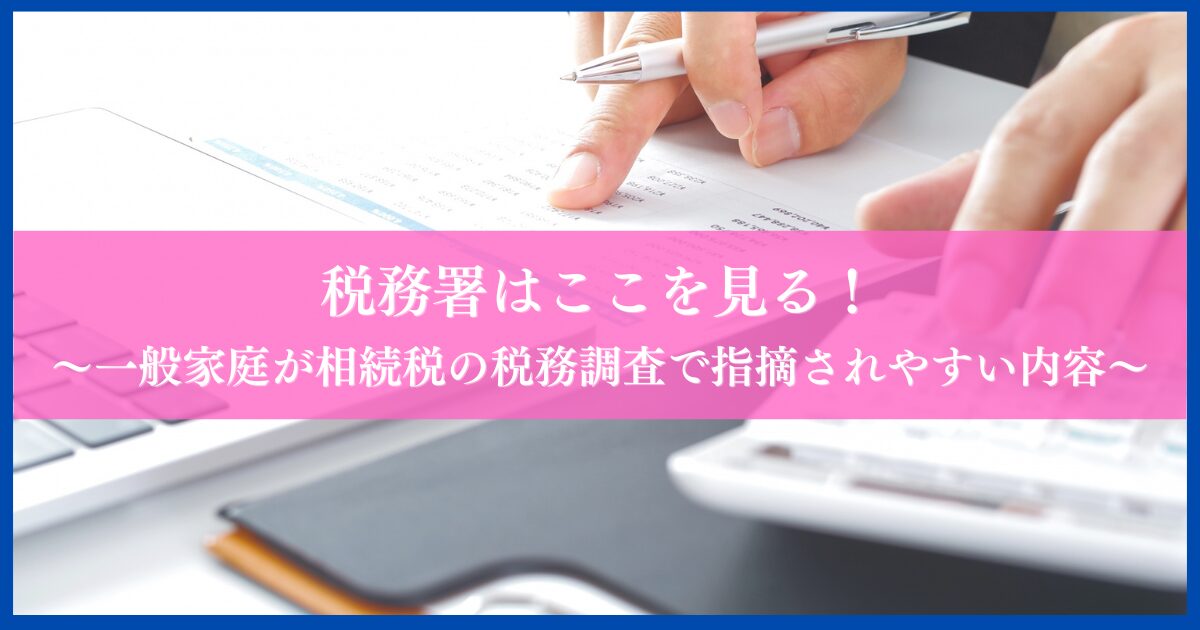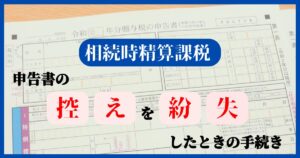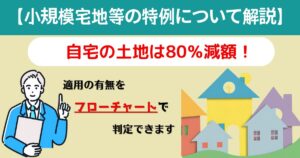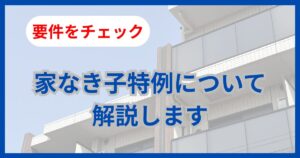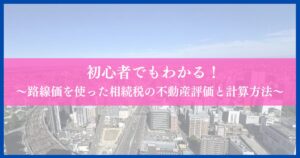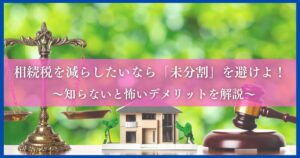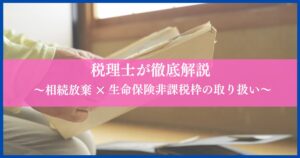相続税の税務調査と聞くと、「うちは資産家ではないから関係ないだろう」と思われる方もいるのではないでしょうか。
ところが、相続税の税務調査の対象は必ずしも資産家や大地主に限られません。
実際に一般家庭でも調査を受けるケースは珍しくありません。
そして国税庁の統計では税務調査の対象になった申告のうち、約8割以上で申告漏れが発見されています。
この記事では、「一般家庭が相続税の税務調査で指摘されやすい内容」や「相続税申告を税理士に依頼するメリット」をわかりやすく解説します。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続税の税務調査の確率
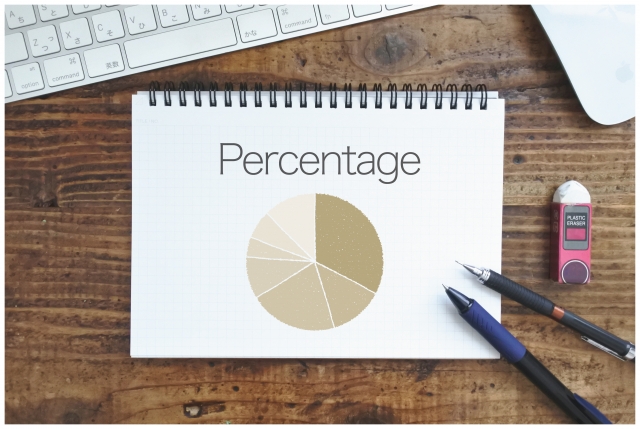
国税庁は相続税の申告件数と税務調査件数を毎年公表しています。
令和5事務年度における相続税の税務調査件数は8,556件でした。
申告を行ってから税務調査が行われるまでにタイムラグがあるため、令和5年の税務調査件数を令和3年の申告件数で割って計算を行うと、税務調査の確率は6.4%(8,556件/134,275件)になります。
※令和3分における相続税申告件数は134,275件
そして令和5事務年度における申告漏れ等の非違件数(申告ミスがあった件数)は7,200件あります。
つまり、84.2%(7,200件/8,556件)は税務調査により何らかの指摘を受けていることになります。
以上のことから、昨今においては相続税の調査確率は比較的高くはないものの、調査の対象になった場合は指摘を受ける可能性が非常に高いことがわかります。
相続税の税務調査に選ばれる人の特徴

相続税の税務調査は限られた調査職員や調査日数の中で行われます。
そのため膨大な申告件数の中から調査先をある程度絞り込む必要があります。
では、税務署が調査先を選ぶ基準にはどのようなものがあるのでしょうか。
それは主に次のような場合です。
(1)申告内容に間違いが多い
申告内容に間違いが多い場合は税務調査に選ばれる確率が高まります。
軽微な間違いであれば、税務署からの確認や申告書の再提出などで済むこともありますが、あまりにも間違えている部分が多い場合は、そもそも意図して過少に申告しているのではと疑われやすくなります。
(2)税務署が得ている情報と申告内容に差がある
過去の所得税や贈与税の申告との整合性が取れていない場合や、金融機関・不動産登記から得られる情報と申告内容に差がある場合は税務調査に選ばれる確率が高まります。
例えば、所得税の確定申告で毎年多額の収入があったにもかかわらず、相続財産に現預金が極端に少ない場合などは整合性が取れていないと判断される可能性があります。
また、不動産登記の情報から、数年前に不動産を売却しているにもかかわらず、現預金がまったくないといった場合も同様に整合性が取れていないと判断される可能性があります。
(3)会社役員、医師、弁護士などの高額所得者
会社役員、医師、弁護士などは生前の所得が高額であることが多く、資産運用によって多数の資産を保有している場合が多いため、調査の対象になりやすい傾向があります。
(4)無申告
無申告とは、相続税の申告義務があるにもかかわらず、申告・納税をしていない状態のことです。
税務署は亡くなった人の生前の所得や財産についての情報をある程度、把握することができます。
そのため無申告の場合は調査の対象になりやすくなります。
(5)税理士の関与無しで相続税申告を行った
相続税の申告を「自分でやってみた」というケースでは、税務調査に入られる割合が高くなります。
その理由は、
・土地などの財産評価に誤りが起きやすい
・名義預金などの判断基準を誤解している
・非課税枠や特例の適用要件を満たしていないことが多い
といった計算や判断の不備が多いためです。
税務署もこの点を把握しており、「税理士が関与していない申告=リスクが高い」として重点的に調査対象に挙げることがあります。
ここまで解説した通り、税務調査は「疑わしい案件や申告漏れの可能性が高い案件を絞り込んで行われる」ため、選ばれた家庭は一般家庭であったとしても高確率で指摘を受けやすいのです。
一般家庭で指摘されやすい内容

ここからは、相続税の税務調査で一般家庭が指摘されやすい内容を確認していきます。
(1)名義預金
相続税の税務調査のメインターゲットは間違いなく「名義預金」です。
名義預金とは、簡単に言うと「亡くなった人が他人名義で所有していた預金口座」のことをいいます。
・子ども名義の口座に親が入金していた
・通帳や印鑑を親が管理していた
・子ども自身はその口座を使っていなかった
これらのケースは「実質的に親の財産」と判断され、相続財産に加算されます。
つまり、名義人ではなく、真の所有者が誰なのかという視点で判断されることになります。
真の所有者は誰なのかという判断は非常に難しい部分ではありますが、主に次の要素から総合的に判断されます。
通帳はその所有者の権利を証する書類といえます。
亡くなった人が通帳を保管し、名義人は預金の存在を知らない又は知っていたとしても名義人の手元にない場合は、実質的に亡くなった人が所有者ではないかと考えられます。
印鑑の保管者も通帳の保管者と同様に重要な要素になります。
口座の開設と解約には印鑑が必要であるため、印鑑の保管者が真の所有者ではないかと疑われます。
財産は所有者が自己管理を行うのが原則です。
別居している子や孫名義の預貯金の手続きを亡くなった人が行っていた場合、名義預金として指摘を受ける可能性が高くなります。
名義人の所得の確認は必ず行う必要があります。
名義人に所得がないのにもかかわらず、名義人の口座に多額の金額が預けられている場合は、その原資の確認が必須になるでしょう。
贈与が行われていたかどうかも名義預金の判定において重要な要素になります。
贈与が行われていた場合は贈与を受けた人の財産になるため、名義預金として相続税の申告に計上する必要はありません。
ですが、相続の現場でよくあるのが「贈与を行っていたつもりだが、贈与が成立していなかった」ということです。
民法549条によると、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。
つまり、「財産をあげます」「財産をもらいます」とお互いが意思表示することで、贈与は成立するのです。
親が子の知らないところで子名義の口座に預金をしているというのはよくある話ですが、これがまさに「名義預金」なのです。
相続税の税務調査の際に、「この預金の存在を知っていましたか?」と質問された際に、「知らなかった」と答えた場合は、「財産をもらいます」と意思表示ができていなかったと判断されてしまいます。
この場合は贈与が成立していないと捉えられ、「名義預金」として相続財産に加算されてしまいます。
名義預金がある方は早めに解消しておくことをおすすめします。
その方法について詳しくは次の記事で解説しています。
(2)名義保険
名義保険も相続税の税務調査で指摘されやすい項目の1つです。
名義保険とは保険契約者と保険料の負担者が異なる保険契約のことです。
例えば、保険契約者が子であるにもかかわらず、親が保険料を負担していた場合などです。
上記のようなケースでは保険契約者である子が被保険者になっている場合が多く、親が亡くなったときは保険金がおりないことから、一見すると相続税には関係がないように思えます。
しかし、保険料を負担していたのは親であることから、親が亡くなった場合は、その時点の解約返戻金相当額を「みなし相続財産」として相続税に計算に含める必要があります。
(3)贈与財産
相続税の税務調査では「贈与財産」の計上漏れがないかを確認されます。
なぜなら相続税の申告には、次の通り贈与財産を加算しなければならない場合があるためです。
①生前贈与加算
被相続人から亡くなる前3年以内(令和6年以降は7年以内)に受けた贈与財産は、原則として相続財産に加算しなければなりません。
これを生前贈与加算といいます。
特に贈与税の基礎控除である年間110万円以内の贈与の場合は贈与税の申告を行う必要もないため、贈与を受けたことを失念していて計上漏れになる場合が多いです。
②相続時精算課税適用財産
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた財産は、相続財産に加算しなければなりません。
しかし、実際には、過去に相続時精算課税制度を使ったことを相続人がよく把握しておらず、相続税の申告書に記載していないケースが少なくありません。
たとえば、「以前に父が税理士を通して贈与の手続きを行ったが、書類を紛失した」などの場合は、税務署側が過去の贈与税申告の内容を調べて、相続財産に加算するように指摘してくることがあります。
相続時精算課税制度の書類を紛失した場合の手続きについて詳しくは次の記事で解説しています。
また、贈与税について詳しくは次の記事で解説しています。
(4)多額の出金
生前に多額の出金がある場合は、手元に現金が残っている可能性や贈与があったかどうかなどを確認されます。
特に相続開始直前は葬式費用の準備のために、多額の出金が行われることが多い傾向にあります。
このような場合は相続財産に「現金」を計上しなければなりません。
そのうえで葬式費用は「債務控除」を行うことになります。
もしも、相続財産に「現金」を計上せずに、「亡くなった日の預金残高」のみを相続財産に計上し、葬式費用を「債務控除」した場合は二重で債務控除を行っていることになりますので指摘されます。
また、よくあるのが認知症の親の口座から相続人の口座へ資金移動しているケースです。
これは相続人としては贈与で「もらった」という認識であることが多いのですが、認知症の人は原則、「あげます」と意思表示ができません。
つまり、贈与が成立していない状態です。
このような場合は、相続人の口座に移動したお金は「貸付金」や「預け金」として相続財産に計上する必要があるのです。
当事務所の事例を紹介

(1)名義保険を正しく申告した事例
相続税の申告をご依頼いただいたお客様より保険契約がたくさんあるとのご報告を受け、家族名義の保険契約も合わせて確認。
すると、契約者がご家族名義の保険契約のうち、複数の保険契約の保険料が被相続人の口座から引き落としになっていたことが発覚。
名義保険に該当することから、すぐに保険会社から亡くなった日の解約返戻金に関する資料を取り寄せていただき、名義保険として正しく申告することができました。
(2)税務調査において贈与財産の加算を防いだ事例
相続税の税務調査において、贈与を受けた事実が明白な現預金を貸付金として相続財産に計上し、修正申告をすべきだと指摘される。
たしかに相続人は贈与税の申告を行っていなかったため、一定の落ち度はあるものの、贈与税の申告がなかったことをもって、贈与の事実がなかったことにはならないと反論。
また、相続人と被相続人は借用書を取り交わしていた事実もないことや返済するという認識もなかったことから、結果として贈与を受けた現預金は相続財産に計上しないことになり、税務調査が終了しました。
相続税の税務調査においては過去の贈与を無理やり相続財産に加算しようとする傾向があるため、事実関係を整理して正しく説明することが重要になります。
※本ケースでは贈与税の時効も過ぎていたため、贈与税の納税も発生しませんでしたが、贈与を受けた場合は贈与税の申告を正しく行うことが必要になります。
相続税申告を税理士に依頼することで得られる3つのメリット

相続税申告は一見「書類を集めて申告書を作るだけ」と思われがちですが、実際には「財産の評価」「税務上の判断」「根拠の説明」という3つの力が問われます。
これらを適切に行うためには、税理士の専門的知識と実務経験が欠かせません。
(1)財産の評価を適正に行い、税額を抑えられる
相続税の計算では、土地や非上場株式など「評価に幅がある財産」が多く含まれます。
税理士はその中で減額要因を検討しながら評価を行います。
結果として数百万円単位の節税に繋がるケースも珍しくありません。
たとえば、土地の評価では、
・地形や間口、奥行きなどの形状要因の反映
・小規模宅地等の特例の適用
など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。
これらを一般の方がご自身で判断するのは非常に難しいのが実情です。
土地の評価や小規模宅地等の特例については次の記事で解説しています。
(2)税務調査を受けにくい「論理的な申告」ができる
税務署は、申告書の内容や添付資料を見て「不自然な点があるか」を瞬時に判断します。
たとえば、財産評価や贈与財産、名義預金など疑わしい部分があれば調査の候補に挙げられやすくなります。
税理士が関与していればそのような部分を検討し、網羅したうえで申告を行うため調査のリスクを大幅に下げられます。
実際、「税理士の署名押印がある申告書」と「本人が作成する申告書」では、後者のほうが明らかに調査率や追徴税額が高い傾向にあります。
(3)「調査になっても安心」の説明体制がある
税務調査で重要なのは「申告書の根拠を説明できるかどうか」です。
税理士が関与していれば、財産評価の根拠や、贈与財産の確認、名義預金などについてあらかじめ精査したうえで申告を行うため、調査が行われても一貫した説明が可能です。
また、税務調査の際には税理士が同席し、やり取りや説明も代理してくれます。
相続人が直接的に対応する必要がないため、精神的な負担も大幅に軽減されます。
このように税理士に依頼する最大のメリットは正確な申告と安心のサポート体制にあります。
相続税の税務調査は「運」ではなく「準備」で防ぐことが可能です。
まとめ
相続税の税務調査は、資産家だけでなく一般家庭にも及びます。
特に名義預金・名義保険・贈与財産・多額の出金は指摘されやすい部分です。
事前に整理して、税理士に相談することが最大の防衛策と言えるでしょう。
「うちは一般家庭だから大丈夫」と思わずに、早めに準備を進めることをおすすめします。