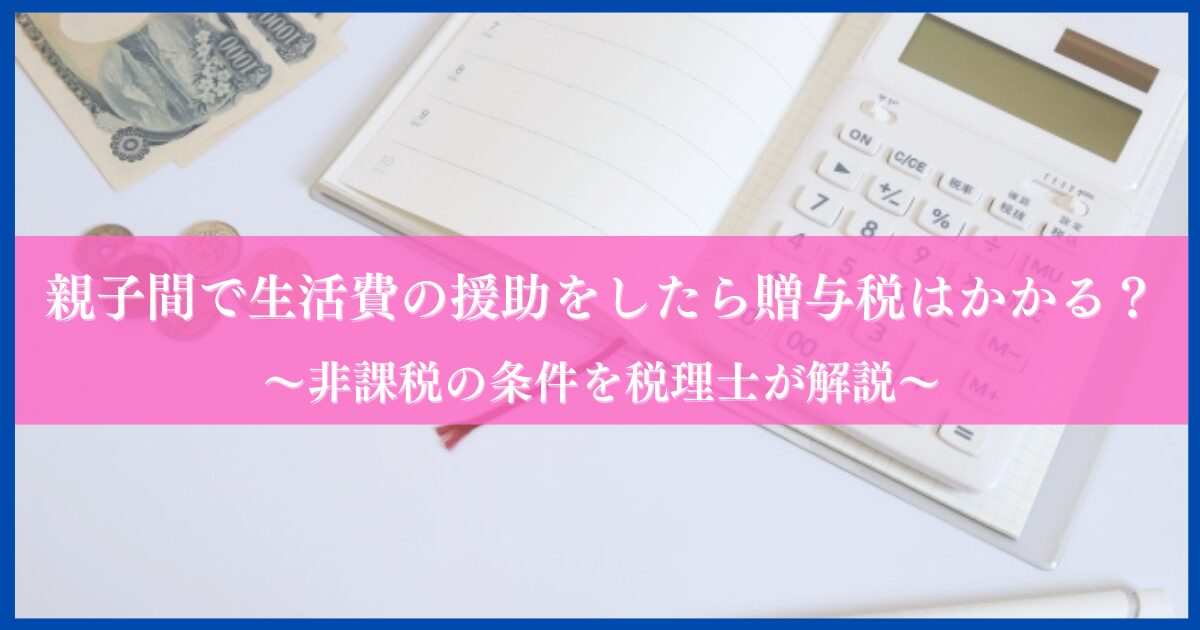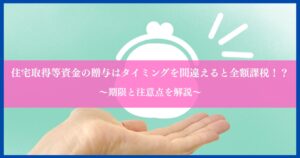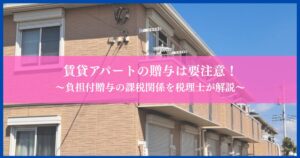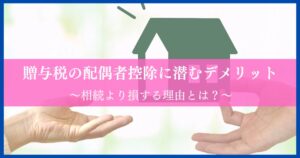親が子どもに仕送りをしたり、学費を負担したりすることは珍しいことではありません。
大学進学の仕送り、留学費用の負担、社会人になるまでの生活支援など、親子間でお金のやり取りが生じる場面は多いでしょう。
しかし、ここで気をつけなければならないのが「贈与税」の存在です。
生活費や教育費の贈与は原則として非課税とされていますが、援助の方法や金額によっては課税対象になる場合もあります。
本記事では親子間における生活費の援助が贈与税の対象になるかどうか、その境界線をわかりやすく解説します。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
贈与税の基本

まずは贈与税の基本的な仕組みを押さえておきましょう。
贈与税とは個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。
年間110万円までは基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。
しかし、年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与を受けた金額に応じて、10%~55%の贈与税が課税される可能性があります。
「親子間だから問題ない」と思っても、お金のやり取りをしたら贈与税の対象になってしまうのです。
贈与税について詳しくは次の記事で解説しています。
親子間における生活費の援助は原則として贈与税が非課税

では、親子間で生活費や教育費を渡した場合、すべて贈与税の対象になるのでしょうか。
実は、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で通常必要と認められるもの」は贈与税が非課税になります。(相続税法第21条3第1項第2号)
ここでいう、「生活費に充てるためにした贈与」とは、生活費として必要な都度行われるものでなければなりません。
また、「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた人の需要と贈与をした人の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲のことをいいます。
簡単に言うと、生活費をその都度、常識の範囲内で渡す分には贈与税は非課税になるということです。
例えば、親が大学生の子に生活費として毎月100万円を渡しているといった状況の場合は、社会の常識の範囲を明らかに超えているため非課税にはなりません。
大学生に毎月100万円が通常必要であるとは言えないということです。
扶養義務者の範囲

「扶養義務者相互間において生活費又は教育費にに充てるためにした贈与により取得した財産で通常必要と認められるもの」は贈与税が非課税になると解説しました。
「扶養義務者」とは次の人たちをいいます。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
・三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは贈与時の状況により判断します。
贈与税が非課税になる生活費や教育費とは?

次のような生活費や教育費については贈与税が非課税になります。
・医療費や入院費用の負担
・同居している子や親の食費・光熱費の負担
・別居している親から子又は子から親への仕送り(金額が妥当である場合)
・学校への入学金・授業料の支払い(義務教育に限らない)
・教材代、通学定期券、部活動の費用
日常生活でかかる費用や教育にかかる費用のほとんどが非課税になります。
ただし、必要な分をその都度渡す、負担するのというのが重要です。
生活費や教育費を非課税で贈与する際の注意点

(1)贈与のやり方
生活費や教育費に充てるためとして、一括で贈与を行った場合には非課税になりません。
生活費や教育費は必要な都度渡し、家賃や学費などであれば不動産会社や学校の口座に直接振り込んだほうがよいでしょう。
(2)実際の扶養の有無は関係ない
扶養義務者相互間とは、扶養義務のある者同士であって実際に扶養している・扶養されているということは関係ありません。
また、社会保険や所得税の扶養親族に該当しているかが求められているわけでもありません。
例えば、社会保険の適用上、子が親の扶養に入っている場合であっても、祖父母がその子(孫)に対して生活費や教育を贈与したとしても、通常必要と認められるものの範囲内であれば贈与税は非課税になります。
(3)金額の制限は設けられていない
贈与税が非課税になる生活費や教育費については、金額による制限が設けれていません。
1回に渡す金額が○○円までは非課税といったことを決めてしまうと、実際に生活費や教育費で使用しないにも関わらず、その上限額を非課税で渡してしまおうと考えてしまう人が出てくるため、社会通念上適当と認められる金額、すなわち常識に照らして判断するという決まりになっています。
非課税にならないケース

生活費のつもりだったのに課税対象になっているケースも少なくありません。
次のような場合は贈与税の課税対象になる可能性が高いです。
(1)多額の現金をまとめて渡す場合
多額の現金をまとめて渡す場合は非課税になりません。
例えば子どもに対して「大学4年間分の生活費や学費」を一括で子の口座に振り込むといった場合です。
生活費や学費が非課税になるためには「必要な都度」贈与する必要があります。
たとえ生活費や学費として使用すると見込まれる場合であっても、数年分を一括で振り込んだ場合は非課税にならないでしょう。
(2)投資や貯蓄に回っている場合
生活費や教育費として渡したお金が、投資や貯蓄に回っている場合は非課税になりません。
例えば、子どもが親からの仕送りに手をつけず、自分で稼いだお金を生活費に充てたような場合です。
非課税になるためには、生活費としての仕送りはその都度、生活費として使いきっている必要があります。
また、生活費として受け取ったお金でブランド品などを購入した場合も非課税になりません。
(3)住宅取得資金に充てた場合
「生活に必要だから」という理由で親から受け取ったお金を住宅取得のために使用した場合は、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で通常必要と認められるもの」には該当せず贈与税の課税対象になります。
ただし、住宅取得のための資金は一定の手続きを行うことで、非課税にすることができます。
これを「住宅取得等資金の贈与税の非課税」といいます。
詳しくは次の記事で解説しています。
相続税対策と生活費援助の関係

生活費援助を利用して「相続税対策になるのでは?」と考える人もいるのではないでしょうか。
実際、ここまで説明した内容に注意して正しい方法で生活費を渡せば自分の財産は減少することになるため、結果として相続税対策になるかもしれません。
しかし、注意が必要です。
もしも、生活費として子どもの口座に毎月入金していたとします。
ですが、その口座は自分が管理していて子どもは口座の存在も知らない場合はどうなるでしょうか。
それは生活費として子どもに渡していたことにならず、「名義預金」に該当します。
名義預金とは、自分が他人名義で預金している預金口座のことをいいます。
名義預金に該当する場合は、自分の相続財産になるため、相続税対策にはなりません。
そして相続税申告のときに名義預金を相続財産に計上しないと、税務署に指摘されてしまいます。
もしも名義預金がある人は相続時のトラブルを防止するため、早いうちに解消しておくことをおすすめします。
名義預金の解消方法は次の記事で解説しています。
Q&A

(1)生活費でも110万円を超えたら贈与税がかかりますか?
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
この範囲内であればどんな財産を贈与しても贈与税はかかりません。
ですが、生活費や教育費の非課税は基礎控除とは別に設けられているため、生活費や教育費が110万円を超えても非課税になります。
ただし、必要な分をその都度渡した場合に限ります。
(2)帰省時に親から交通費を貰いましたが、贈与税がかかりますか?
帰省時の交通費は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費にに充てるためにした贈与により取得した財産で通常必要と認められるもの」に該当すると考えられますので、贈与税はかからないでしょう。
なお、実費を大幅に超える金額を受け取った場合は、贈与税がかかる可能性があります。
(3)生活費を多めに渡しても税務署にバレないのではないでしょうか?
税務署は親子間のお金の動きを注視していますので、バレる可能性があります。
特に相続税の税務調査時は被相続人と相続人の過去10年分の預金の動きをチェックされるため、生活費にふさわしくない多額の資金移動があればすぐにバレてしまいます。
まとめ
親子間での生活費や教育費の援助は、税法上「必要な都度、必要な範囲であれば非課税」とされています。
学費や家賃、医療費などは一般的に認められますが、大きな金額を一括で渡したり、渡したお金が貯蓄やぜいたく品に使われると贈与税の課税対象になるリスクがあります。
また、安易に「相続税対策になる」と考えるのは危険で、かえって名義預金として相続財産に加算されることもあります。
非課税のルールを正しく理解して、安心できる生活費援助を行いましょう。