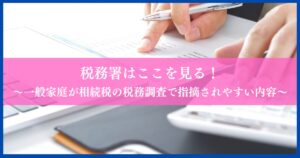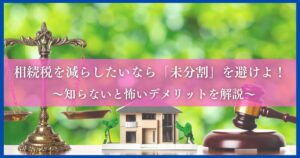「配偶者は財産を相続しても1億6千万円まで相続税がかからない」という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
実際その通りで、配偶者は「配偶者の税額軽減」という制度(一般的に「配偶者控除」といいます)によって1億6千万円まで相続税が非課税になります。
この制度は故人の財産形成に対する配偶者の貢献度や配偶者の今後の生活保障のために設けられています。
この話を聞いて、相続税がかからないように「配偶者に全財産を相続させるように遺言書を残そう」、「遺産分割協議で故人の配偶者が全財産を相続することにしよう」と考える人が多いと思います。
しかし、この財産の分け方が相続税の負担を最も大きくしてしまう可能性が高いのです。
本記事では配偶者控除の要件や注意点、活用する際のポイントについて解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。
配偶者は1億6千万円または法定相続分まで相続税が非課税
冒頭で配偶者は1億6千万円まで相続税が非課税という話をしました。
実際には1億6千万円と法定相続分のいずれか大きい金額まで非課税ということになっています。
配偶者の法定相続分は次の通りです。

言葉での説明だけですと難しいと思いますので実際に数字を使って確認しましょう。
相続財産が3億円で相続人が配偶者と子の場合
1億5千万円<1億6千万円 ∴1億6千万円まで非課税
この場合、配偶者の法定相続分は1/2で1億5千万円です。
1億6千万円と比較して1億6千万円のほうが大きいので配偶者は1億6千万円まで相続しても非課税になります。
相続財産が6億円で相続人が配偶者と子の場合
3億円>1億6千万円 ∴3億円まで非課税
この場合、配偶者の法定相続分は1/2で3億円です。
1億6千万円と3億円を比較して3億円のほうが大きいので配偶者は3億円まで相続しても非課税になります。
配偶者控除の適用要件

次は配偶者控除の適用要件について確認していきます。
(1)婚姻の届出をしていること
配偶者控除の適用を受けることができるのは亡くなった人と婚姻の届出をしている戸籍上の配偶者に限られます。(外国籍の人でも問題ありません。)
事実上婚姻関係と同様の事情にある人でも婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係にある人は適用を受けることができません。
なお、配偶者が相続の放棄をした場合でも、遺言書によって財産を取得するときや生命保険金の受取人になっているときなどは適用を受けることができます。
(2)相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していること
配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告期限(相続開始の翌日から10か月)までに遺産分割協議が終了している必要があります。
遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分け方を決めることを言います。
もしも、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合は、相続人が法定相続分で財産を取得したものと仮定して相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
その際は、配偶者控除の適用を受けることができないため、多額の相続税を支払うことになってしまいます。
その後、遺産分割協議が終了した場合、配偶者控除を適用し、更正の請求と呼ばれる一定の手続きをしたときは納めすぎた相続税を戻してもらうことができます。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合は配偶者控除の適用を受けることができず、最初に余分な相続税を支払わなければならないため、遺産分割協議は早めに終了させるのが望ましいでしょう。
(3)相続税の申告書を税務署に提出すること
配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
配偶者控除を使って相続税が0円になったとしても必ず申告書を税務署に提出する必要があります。
なお、相続税の申告書には次の書類を添付する必要があります。
添付書類
・亡くなった人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)又は法定相続情報一覧図の写し
・遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
配偶者控除の注意点

ここまで配偶者控除の計算や適用要件について解説しました。
解説を見て、「配偶者がすべての財産を相続すれば相続税を少なくできて安心だな」と考えた人も多いのではないでしょうか。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
次は配偶者控除の注意点について解説していきます。
(1)相続税は一次相続と二次相続の合計で考える
一次相続とは両親のうち一方が亡くなった際に、配偶者や子に財産が相続されることを言います。
二次相続とは残された親が亡くなり、子に財産が相続されることを言います。
相続税は二次相続のほうが高くなる傾向があります。
つまり、一次相続で配偶者に多くの財産を相続させた場合、配偶者控除によって一次相続の相続税は安くすみますが、二次相続の相続税が高くなってしまい、トータルで考えたときに損をしてしまう可能性があります。
二次相続の相続税が高くなる理由は主に次のようなものです。
①配偶者が元々所有していた財産の影響
配偶者が元々所有していた財産と一次相続で相続した財産の合計に対して二次相続の相続税がかかります。
②相続人が1人減少するため基礎控除が少なくなる
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。
二次相続の際は配偶者がいないため、基礎控除が減少します。
③生命保険金の非課税枠が少なくなる
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
二次相続の際は配偶者がいないため非課税枠も少なくなります。
④相続税の税率が高くなる
相続税は相続財産の金額が大きくなるほど税率が高くなる超過累進税率が採用されています。
①~③の影響により課税される相続財産の金額が大きくなるため相続税率が高くなります。
(2)具体例で確認
配偶者控除の注意点について具体例で確認してみます。
亡くなった人:父
相続人:配偶者と子
相続財産:1.5億円
※配偶者に固有の財産はなく、一次相続から二次相続までのあいだの財産の増減は考慮しないものとします。
< 一次相続で配偶者が全財産を相続する場合 >
一次相続の相続税:0円
二次相続の相続税:2,860万円
一次相続と二次相続の相続税合計:2,860万円
< 一次相続で配偶者が法定相続分1/2を相続する場合 >
一次相続の相続税:920万円
二次相続の相続税:580万円
一次相続と二次相続の相続税合計:1,500万円
上記の具体例のように一次相続で配偶者が全財産を相続して配偶者控除を最大限活用した結果、一次相続と二次相続の相続税合計で見ると大きく損をしていることがわかります。
このように配偶者が全財産を相続して配偶者控除を最大限活用することが必ずしも最適解になるというわけではありません。
では、配偶者控除をどのように活用すれば良いのかについて次の章で解説していきます。
配偶者控除を活用する際のポイント

(1)一次相続で配偶者にいくら相続させるのかを検討する
先ほどの具体例では一次相続で配偶者が全財産を相続する場合と法定相続分で相続する場合で相続税を比較しました。
ご家庭ごとに配偶者が相続財産のうちどのくらい相続すると相続税が安くなるといった最適解が存在します。
相続財産の金額や相続人の人数などによってその最適解は異なりますが、シミュレーションを行うことで最適解を見つけることができます。
しかし、そのシミュレーションの際は、配偶者が元々所有している「配偶者固有の財産」や「今後の財産の増減」も考慮しなければいけない場合があります。
その辺りのことも考慮して細かくシミュレーションをしたい場合は税理士に相談することをおすすめします。
二次相続のシミュレーションについて詳しくは次の記事で解説しています。
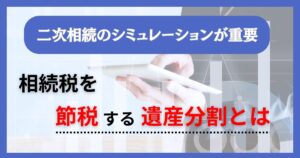
(2)配偶者にあえて財産を多く相続させて二次相続対策を行う
配偶者が相続対策に積極的な場合は配偶者にあえて財産を多く相続させて二次相続対策を行いましょう。
配偶者が一次相続で財産を多く相続すれば配偶者控除により、一次相続の相続税は安くなります。
そして二次相続までの間に配偶者が相続対策を行うことで、二次相続の相続税を減らすことが可能です。
配偶者がまだそこまで高齢でない場合や相続対策に積極的な場合は検討してみましょう。
相続対策として取り組みやすいものは生命保険への加入や生前贈与などがあります。
詳しくは次の記事で解説していますので参考にしてみてください。
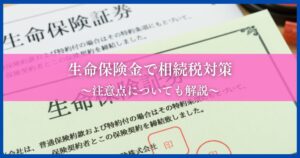

(3)配偶者に全財産を相続させるという遺言書が見つかった場合
ここまでの解説により、一次相続で配偶者にどのくらい財産を相続させるかがポイントであることは理解していただけたのではないでしょうか。
しかし、相続後に「全財産を妻に相続させる」といった内容の遺言書が見つかる場合もあるかと思います。
そのような場合は相続人全員が合意することで遺言書と異なる遺産分割を行うことが可能です。
相続人全員で遺産分割協議を行うことで、一次相続と二次相続のトータルの相続税が少なくなるように遺産分割を調整することができます。
ただし、遺言書通りに遺産を分割して故人の意思を尊重するか、遺言書と異なる方法で遺産を分割して相続税の負担を減らすようにするかは、ご家庭によって様々な考え方がありますので慎重に検討しましょう。
配偶者控除に関するよくある質問

(1)配偶者が認知症の場合は適用できますか?
認知症の人は遺産分割協議に参加できないため、後見人を選任して遺産分割協議を行うことになります。
後見人が遺産分割協議に参加し、相続税の申告書を提出すれば配偶者控除は適用できます。
(2)申告期限までに遺産分割が確定していない場合はどうすれば良いですか?
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、まずは法定相続分で財産を取得したものとして申告を行います。
その後、3年以内に遺産分割が確定した場合は更正の請求を行い、配偶者控除を適用すれば納めすぎた相続税を戻してもらうことができます。
(3)期限までに相続税の申告をしていなかったのですが適用できますか?
申告期限を過ぎた後でも相続税の申告書を提出すれば配偶者控除は適用できます。
まとめ
本記事では相続税の配偶者控除について解説しました。
配偶者控除は相続税を大きく節税できる制度です。
ただし、二次相続まで考慮して活用しないと大きく損をしてしまう可能性があります。
配偶者控除を適切に活用して相続税を節税したいという人は税理士に相談することをおすすめします。