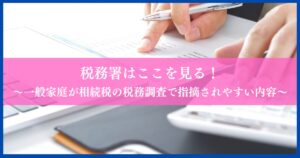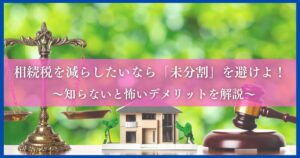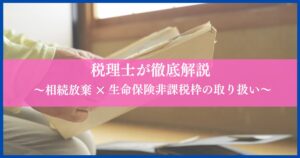相続で受け継いだ財産をそのまま公益団体や自治体に寄付すると、その寄付した財産について相続税がかからない特例があります。
「社会のために役立てたい」
「相続税の節税も考えたい」
そのような想いを叶えられるのが、相続財産を寄付した場合の非課税制度です。
ただし、非課税の適用を受けるためには寄付先、期限、財産の種類など細かい要件を満たす必要があります。
本記事では、非課税制度の概要、対象となる寄付先、手続き、注意点などをわかりやすく解説します。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続財産を寄付した場合の非課税制度とは

相続財産を寄付した場合の非課税制度とは、相続や遺贈により取得した財産を、国や地方公共団体、公益法人等へ寄付した場合、その寄付した財産は相続税が非課税になる制度のことです。
非課税の対象になる財産は次の通りです。
・相続財産そのもの(不動産、預貯金、株式など)
・生命保険金(みなし相続財産)
・死亡退職金(みなし相続財産)
相続や遺贈で取得した財産そのものを寄付することが要件の1つで、相続財産を売却して現金を寄付した場合は非課税の対象外になります。
非課税が適用されるための要件

相続税が非課税となるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)相続や遺贈により取得した財産であること
寄付する財産は亡くなった人から取得した財産でなければなりません。
第三者から譲り受けた財産や、自分が元々所有していた財産を寄付しても相続税は非課税になりません。
(2)寄付先が一定の公益団体などであること
どこに寄付しても相続税が非課税になるわけではありません。
国税庁が定める一定の公益団体などへの寄付が非課税の対象になります。
詳細については後述します。
(3)相続税の申告期限内に寄付を行うこと
相続財産の寄付は相続税の申告期限内に行う必要があります。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。
それまでに寄付の相手先に連絡をして、寄付を行い、寄付金受領証明書などを発行してもらう必要があるため、迅速な対応が必要になります。
(4)相続財産そのものを寄付すること
寄付をする際に相続財産を現金化してはいけません。
例えば、相続した不動産を売却して、売却によって得たお金を寄付した場合などは非課税の対象になりません。
不動産なら不動産そのものを、株式なら株式そのものを寄付する必要があります。
もちろん、現金や預貯金であっても、相続した現金や預貯金であれば非課税の対象になります。
(5)寄付金受領証明書などを相続税の申告書に添付すること
非課税の適用を受けるためには、寄付先が発行する寄附金受領証明書などを相続税の申告書に添付する必要があります。
相続税が非課税となる寄付先

相続税が非課税となる寄付先は、国、地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる法人(特定の公益法人)などです。
列挙すると次の通りです。
・国、都道府県、市区町村
・独立行政法人
・国立大学法人および大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人で一定のもの
・公立大学法人
・自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社および福島国際研究教育機構
・私立学校法に規定する学校法人で一定のもの
・社会福祉法人
・更生保護法人
・認定NPO法人
※認定NPO法人とは、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認定を受けたものをいいます。
例えば、次のような寄付先であれば相続税が非課税になります。
▼子ども支援
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
フローレンス
▼国際協力
ピースウィンズ・ジャパン
▼災害支援
国際医療技術財団(JIMTEF)
▼医療
日本対がん協会
▼環境保護
日本自然保護協会
手続きの流れ

続いて相続税の非課税の適用を受ける手続きの流れについて解説します。
(1)寄付先の選定と寄付方法の確認を行う
寄付先が非課税の対象になる団体や法人であるかを事前に確認します。
寄付先のホームページなどを確認すると非課税の対象になる団体、法人であるかどうかは把握することが可能です。
また、寄付方法についても記載してあることが多いので合わせて確認し、寄付を行います。
不明な場合は寄付先に電話などで直接問い合わせても問題ないでしょう。
(2)寄附金受領証明書を添付して相続税の申告期限までに申告を行う
相続税の申告書には、下記の情報が記載されている寄附金受領証明書の添付が必要です。
・寄付を受けた旨
・寄付を受けた年月日
・寄付財産の明細
・寄付財産の使用目的
なお、地方独立行政法人又は学校法人に寄付した場合には、上記のほか、特定の公益法人に該当するものであることについて、設立団体又は所轄庁が証明した書類が必要になります。
上記の証明書を寄付先から発行してもらいましょう。
そして、証明書を添付して相続税の申告期限までに相続税の申告を行います。
相続税の申告期限までに申告を行わなかった場合は、非課税の適用を受けることができませんので、余裕を持って手続きを進めて行きましょう。
相続財産の寄付は相続人のふるさと納税の対象にもなる?

相続した財産を都道府県や市区町村などの地方公共団体に寄付した場合は、相続税の非課税とふるさと納税の両方を適用できることになります。
そのため、相続した財産を地方公共団体に寄付した場合には、相続税のみならず、相続人の所得税と住民税も減らすことが可能です。
相続税はいくら節税になる?相続財産を寄付した場合の相続税の計算例

下記のケースで相続財産を寄付した場合、相続税がいくら節税になるか検証してみます。
相続財産:5,000万円
相続人:子1人
▼寄付を行わなかった場合の相続税
課税価格:5,000万円
課税遺産総額:5,000万円-3,600万円(基礎控除額)=1,400万円
相続税:1,400万円×15%-50万円=160万円
▼500万円寄付を行った場合の相続税
課税価格:5,000万円-500万円(寄付額)=4,500万円
課税遺産総額:4,500万円-3,600万円(基礎控除額)=900万円
相続税:900万円×10%=90万円
上記のケースでは、500万円寄付を行うことで相続税を70万円(160万円-90万円)節税することができました。
しかし、相続税が非課税の対象になるのは寄付した分の相続財産のみです。
したがって、相続税の節税効果はそこまで大きいとは言えません。
ですが、前の章でも解説した通り、都道県や市区町村などへ寄付する場合はふるさと納税の対象にもなります。
所得税や住民税の負担を減らすことも考慮するのであれば節税効果を期待できるかもしれません。
なお、相続財産を寄付したことによって、たとえ相続税が0円になったとしても、相続財産を寄付した場合の非課税制度の適用を受けるためには、相続税の申告が必須になります。
まとめ
本記事では相続財産を寄付した場合の相続税の非課税制度について解説しました。
この制度を利用することで、大切な財産を社会に役立てながら、相続税の負担を減らすことができます。
非課税の適用を受けるための要件、寄付先の選定、必要書類の準備、申告までの流れを事前に押さえておくことで、スムーズかつ確実に手続きを進められます。
社会貢献と節税を両立させる第一歩として、この制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。