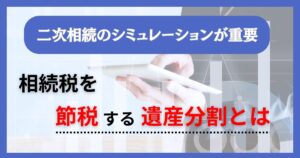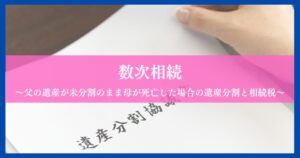遺産分割は亡くなった人が残した遺言書があれば、その内容に従って行うのが基本です。
しかし、実際のところ、遺言書と異なる遺産分割が検討されることが少なくありません。
たとえば次のようなケースです。
・遺言書の作成から年数が経過し、財産の内容や評価額が大きく変化している
・遺言書に記載されている財産がすでに売却されている
・遺言書の内容が一部の相続人にとって極端に不公平
・相続税の負担が増えるような内容になっている
このような場合、「遺言書と異なる遺産分割はできるのか?」という疑問が生じることもあるのではないでしょうか。
本記事では、遺言書と異なる遺産分割を検討する際の、法律上の要件、注意点、節税例などを詳しく解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
遺言書と異なる遺産分割を行うための条件

早速結論ですが、遺言書と異なる遺産分割は原則として可能です。
ただし、次の条件をすべて満たしている必要があります。
(1)相続人全員の同意があること
遺言書と異なる遺産分割を行うためには、相続人全員の同意があることが必要です。
相続人全員が遺言書があること及びその内容を知っていなければなりません。
そのため例えば、遺言書を発見した相続人がその内容を確認したところ、自身に不利な内容が書かれていたため、他の相続人に遺言書の存在を知らせないで、遺言書と異なる遺産分割を行うことはできません。
遺言書の偽造や破棄、隠匿は犯罪行為に該当します。
そのような行為を行った人は相続人の欠格事由に該当し、相続権を失ってしまいますので絶対にやめましょう。
また、相続人が複数いる場合で、1人でも遺言書と異なる遺産分割に反対する場合は、遺言書と異なる遺産分割を行うことはできません。
多数決などではなく相続人全員の同意が必要になります。
(2)相続人以外の受遺者がいる場合、その受遺者も同意していること
遺言書によっては相続人以外の人物に財産を遺贈するといったことが書かれている場合があります。
相続人以外で遺言によって財産を受け取る人のことを受遺者といいます。
この受遺者がいる場合は、受遺者の同意も必要になります。
受遺者の同意がなければ、遺言書と異なる遺産分割を行うことはできません。
(3)遺言執行者がいる場合、遺言執行者も同意していること
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要になります。
遺言執行者とは遺言書に書かれた内容(不動産の名義変更や預貯金の解約など)を実現する人のことをいいます。
遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなることができ、法人や団体、弁護士などの専門家でも遺言執行者になれます。
遺言書において「○○を遺言執行者に指定する」と記載がある場合は、遺言執行者の同意も得なければならないため、注意が必要です。
(4)遺産分割協議を禁じる遺言ではないこと
遺言者は、遺言書によって遺産分割を禁止することができます。(民法908条)
あまり、出てくるような内容ではありませんが、遺産分割を禁止する文言が遺言書に入っていた場合は、たとえ相続人間で同意があったとしても、遺言書と異なる遺産分割を行うことはできません。
(1)~(4)の条件をすべて満たした場合は、遺言書と異なる遺産分割を行うことができます。
なお、その場合は後々のトラブルを防止するために、遺言書の内容を相続人全員が知ったうえで、遺言書と異なる遺産分割をする旨を遺産分割協議書に明記したほうが良いでしょう。
遺言書と異なる遺産分割をした場合の税務上の取り扱い

遺言書と異なる遺産分割をした場合には、その遺産分割協議の内容に応じた相続財産の取得割合でそれぞれの相続人に相続税が課税されることになります。
そのため、一度遺言書によって取得した相続財産を、遺産分割協議によって贈与や交換をしたという扱いにはならず、贈与税などが課税されることは原則としてありません。
ただし、遺言書の内容通りに相続税の申告を行った後や、相続登記をした後に、遺産分割協議を行い、各相続人が取得する相続財産を変動させてしまった場合は、贈与税などが課税される可能性があります。
したがって、遺言書と異なる遺産分割を行う場合は、相続税の申告や相続手続きを行う前に実行する必要があるといえるでしょう。
相続人以外の受遺者がいる場合の注意点

相続人以外の受遺者がいる場合は贈与税に注意が必要です。
相続人以外の受遺者は、本来相続財産を取得する権利はありませんが、遺言書の効力によって相続財産を取得することができます。
逆に言えば、特定の財産を遺贈する内容の遺言書であればその特定された財産しか取得することができません。
例えば株式を遺贈するという内容の遺言書があり、相続人と話し合いの結果、株式を取得することを放棄して、土地を取得したとします。
この場合、相続人以外の受遺者は土地を相続人から贈与で取得したことになるため、相続税の申告ではなく贈与税の申告が必要になります。
つまり、特定の財産を遺贈するとされた相続人以外の受遺者はその財産を取得するか、放棄するかという2択でしか、遺産分割協議には参加できないということになります。
節税事例

遺言書によっては、相続税の負担が増えてしまうような内容になっているケースがあります。
そのような場合は、遺言書と異なる遺産分割を行い、相続税を節税することが可能です。
例えば、配偶者に全財産を相続させるといった内容の遺言書になっている場合は、相続税の負担が大きくなる可能性が高いです。
配偶者は「相続税の配偶者控除」により1億6千万円又は法定相続分のいずれか多い金額の相続まで相続税がかかりません。
したがって、配偶者の全財産を相続させるという内容の遺言書は、相続税の観点からも良いように思えます。
しかし、この内容の遺言書は相続税の負担が最も大きくなる可能性があります。
なぜなら、配偶者が亡くなった時に、高額な相続税が発生するためです。
両親のうち一方が亡くなり、配偶者や子に財産が相続されることを一次相続、残された親(配偶者)が亡くなり、子に財産が相続されることを二次相続といいます。
相続税は一次相続と二次相続のトータルで節税を検討する必要があります。
ここで二次相続のシミュレーションを行い、遺言書と異なる遺産分割を行うことで相続税を節税することが可能です。
相続税の配偶者控除と二次相続のシミュレーションについて詳しくは次の記事で解説しています。
もちろん、必ずしも遺言書と異なる遺産分割を行う必要はありません。
家族で話し合い、故人の意思を尊重して遺言書通りに遺産を分けるという選択も考えられるでしょう。
まとめ
遺言書と異なる遺産分割は、相続人全員の同意があれば原則として可能ですが、そこには多くの注意点が存在します。
遺言執行者や受遺者の同意、遺産分割を禁止する遺言条項、そして税務面でのリスクなど、慎重な判断が求められます。
特に税務上は、意図せず贈与とみなされることで、相続税と贈与税が重複するリスクもあるため、専門的な知見が欠かせません。
実際に手続きを進める際には、相続税申告期限(10ヶ月以内)を意識し、書類作成や関係者との調整も含めてスムーズに進める必要があります。
こうした場面でこそ、税理士など専門家のサポートが大きな力となります。
専門家に相談しながら手続きを進め、安心かつ円満な遺産分割を実現しましょう。