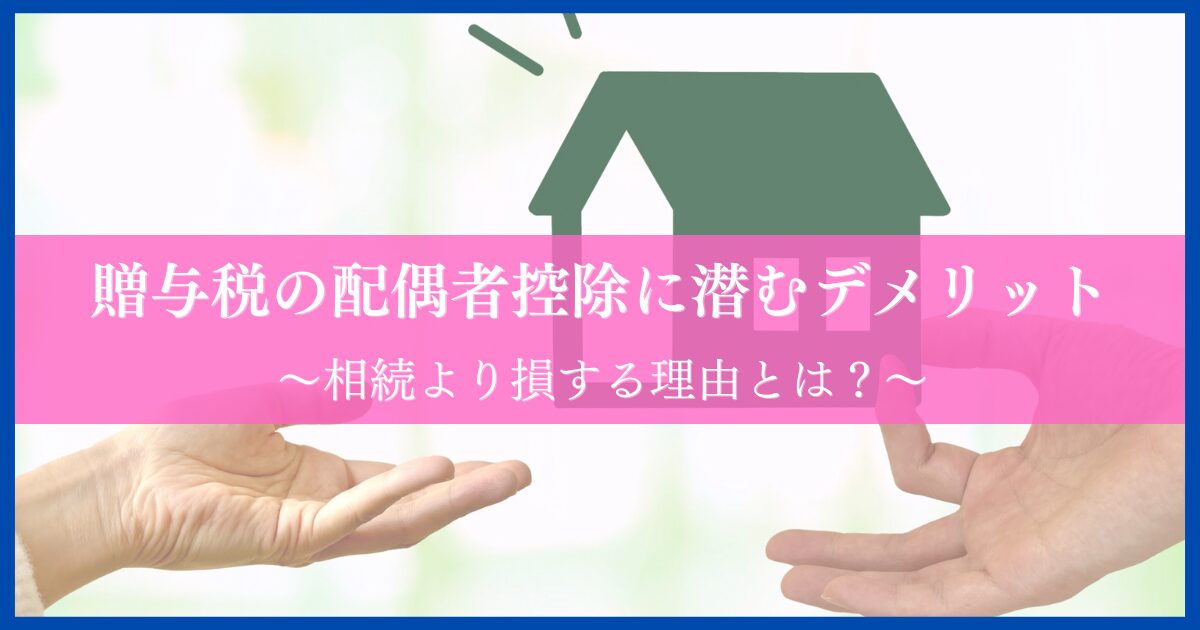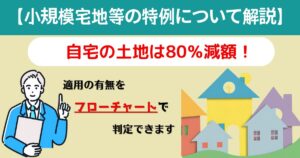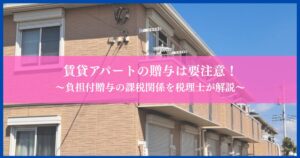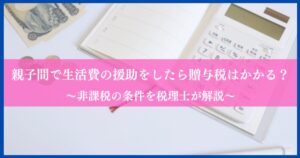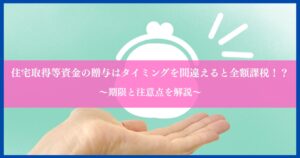「長年連れ添った配偶者に、生前に自宅を贈与したい」
「相続よりも今のうちに財産を整理しておきたい」
そんな思いから活用されることが多いのが贈与税の配偶者控除です。
たしかにこの制度は、最大2,000万円まで贈与税が非課税になるという非常に大きな優遇措置です。
しかし、制度の恩恵ばかりに目が向いてしまうと、かえって損をしてしまうケースが少なくありません。
実は贈与税の配偶者控除には見過ごされがちなデメリットが存在します。
本記事では、制度の詳細やデメリットを徹底的に解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
贈与税の配偶者控除とは?

まずは制度の基本的な仕組みから押さえておきましょう。
(1)制度の概要
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又はその取得資金を贈与した場合に、最大2,000万円まで贈与税がかからないという制度です。
さらに通常の贈与税の基礎控除110万円も併用できるため、合計で2,110万円まで非課税で贈与することが可能です。
(2)適用要件
贈与税の配偶者控除は、上記の要件をすべて満たす場合に適用できます。
(3)計算例
続いて贈与税の配偶者控除を使った場合と使わなかった場合の贈与税の違いを計算例を使って確認してみます。
居住用不動産2,000万円を贈与した場合
▼贈与税の配偶者控除を使った場合
2,000万円(居住用不動産)-2,000万円(贈与税の配偶者控除)-110万円(基礎控除)<0円 ∴贈与税0万円
▼贈与税の配偶者控除を使わなかった場合
(2,000万円(居住用不動産)-110万円(基礎控除))×50%-250万円=695万円(贈与税)
上記の通り、贈与税の配偶者控除を使うことで贈与税をかけずに配偶者に自宅を渡すことができます。
贈与税の配偶者控除のデメリット

贈与税の配偶者控除は、居住用不動産等を2,000万円まで非課税で配偶者に贈与できるため、メリットが大きいと感じる人が少なくありません。
しかし、その一方でこの制度を使うことで税務上のデメリットや将来的なリスクが存在するのです。
続いて、贈与税の配偶者控除のデメリットについて確認していきます。
(1)相続税対策としての効果が少ない
贈与税の配偶者控除は、生前贈与という形で不動産を配偶者に移転する制度です。
しかし相続のタイミングでの取得と比較すると、必ずしも税負担が少なくなるとは限りません。
理由は次の通りです。
①相続時には配偶者の税額軽減という制度が使える
相続税には、配偶者に対して法定相続分又は1億6千万円まで非課税という「配偶者の税額軽減」という大きな優遇制度があります。
仮に配偶者が1億円の財産を相続したとしても、相続税は一切かかりません。
これを考えると諸費用をかけて贈与を行うメリットは少ないといえるかもしれません。
配偶者の税額軽減について詳しくは次の記事で解説しています。
②相続時には小規模宅地等の特例が使える
相続の時は小規模宅地等の特例が使えます。
小規模宅地等の特例とは亡くなった人の自宅の土地を配偶者が相続すると、その土地の評価額が80%減額される特例のことをいいます。
つまり、自宅の土地は通常よりも割安で相続することができます。
小規模宅地等の特例について詳しくは次の記事で解説しています。
以上のことから、贈与税の配偶者控除を使うよりも、相続時に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用したほうが節税になるケースが多いのです。
(2)不動産取得税・登録免許税の負担が増える
贈与により不動産を取得する場合、贈与税の配偶者控除によって贈与税が非課税でも、以下の税金が発生します。
・登録免許税:固定資産税評価額の2%
・不動産取得税:固定資産税評価額の3%(土地は固定資産税評価額を1/2した金額の3%)
これに対して相続で不動産を取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、不動産取得税は非課税になります。
つまり、贈与での不動産の取得は相続に比べて登録免許税と不動産取得税が割高なのです。
※不動産取得税は軽減の特例があるため、3%よりも低くなる可能性があります。
(3)不動産の贈与はコストがかかる
不動産の贈与は、登録免許税や不動産取得税以外にもコストがかかります。
名義変更を司法書士に依頼した場合は数万円~10万円ほど費用がかかります。
また、贈与税の申告を税理士に依頼した場合は10万円程度かかることが多いです。
結果として贈与税はかからないものの、登録免許税・不動産取得税、司法書士、税理士に支払う費用で数十万円、場合によっては100万円くらいかかることもあります。
これらを回収できるほどのメリットがあるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。
デメリットだけではない!贈与税の配偶者控除が有効なケースとは?

前の章で贈与税の配偶者控除のデメリットについて解説しました。
しかし、節税や遺産分割の観点から贈与税の配偶者控除が有効なケースも存在します。
続いて贈与税の配偶者控除が有効なケースについて解説します。
(1)相続時に配偶者の税額軽減を適用しても相続税が大きく課税されるほどの財産があるケース
上記のようなケースにおいてはコストをかけてでも、贈与税の配偶者控除を使って贈与を行うことで相続税を節税できる可能性があります。
また、贈与税の配偶者控除を使って贈与を受けた財産については生前贈与加算の対象にもなりません。
生前贈与加算とは、相続開始前3年内に贈与を受けた財産について、贈与者の死亡時に相続財産に加算しなければならない制度のことをいいます。
贈与税の配偶者控除を使って贈与を受けた財産(2,000万円まで)については生前贈与加算の対象外になります。
(2)土地の面積が330㎡を超えているケース
相続時に使える小規模宅地等の特例は、土地の面積のうち330㎡までが対象になります。
そのため、それを超える面積部分の土地については小規模宅地等の特例が使えず、通常通り評価されます。
そのようなケースでは小規模宅地等の特例の対象にならない、土地の持分の一部を贈与しておくことで相続税の節税につながる可能性があります。
(3)居住用不動産の取得資金を贈与するケース
居住用不動産の取得資金を贈与する場合は、不動産の贈与と異なり、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬が発生しません。
したがって低コストで実行することができ、かつ、相続税対策になる可能性があります。
(4)将来の遺産分割時に配偶者の取り分を確保したいケース
生前贈与は遺産の前渡しです。
これを特別受益といいます。
そのため、贈与を行ったとしても、原則として遺産の前渡しを受けたものとして取り扱われるため、配偶者が取得する財産額は、結果的に贈与がなかった場合と同じになります。
この点について事例を使ってみていきます。
▼事例
相続人:配偶者と子1人
相続時の財産:預貯金8,000万円
配偶者に対する贈与:居住用不動産2,000万円を過去に贈与済み
相続時の配偶者の取り分:(8,000万円+2,000万円)×1/2-2,000万円=3,000万円
相続・贈与合計の配偶者の取り分:3,000万円+2,000万円=5,000万円
上記の通り、贈与は遺産の前渡しを受けたものと取り扱われるため、結局、贈与があった場合とそうでなかった場合とで、最終的な取得額に差異はないことになります。
しかし、2019年7月1日施行の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合には、遺産の前渡しとして扱わなくてよいことになりました。【特別受益の持ち戻し免除の推定規定(民法903条4項)】
改正を踏まえて、先ほどと同様の事例で配偶者の取り分を計算してみます。
相続時の配偶者の取り分:8,000万円×1/2=4,000万円
相続・贈与合計の配偶者の取り分:4,000万円+2,000万円=6,000万円
最終的な取得額は6,000万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より配偶者は多くの財産を取得できることになります。
したがって、配偶者の取り分を多く確保したい場合には、贈与税の配偶者控除を用いた贈与は有効です。
ただし、贈与税の配偶者控除は居住用不動産又は居住用不動産取得資金が対象になりますが、特別受益の持ち戻し免除の推定規定(民法903条4項)は居住用不動産取得資金の贈与は対象になりませんので注意が必要です。
まとめ:贈与税の配偶者控除は慎重に使うべき制度
贈与税の配偶者控除は、「節税になる」と思って安易に使ってしまうと後で大きく損をすることがあります。
・登録免許税・不動産取得税の負担
・相続時の特例との比較
・名義変更に伴うコスト
上記のことを考慮せずに進めてしまうと想定外の結果になりかねません。
贈与税の配偶者控除は決して悪い制度ではありません。
しかし、相続の制度と比較したうえで最適な方法を考えることが必須になります。
財産の内容、家族構成、節税対策、将来の生活設計など総合的な判断が不可欠です。
ご自身にとって本当に徳になる方法を見極めるためにも、まずは税理士などの専門家へご相談することをおすすめします。