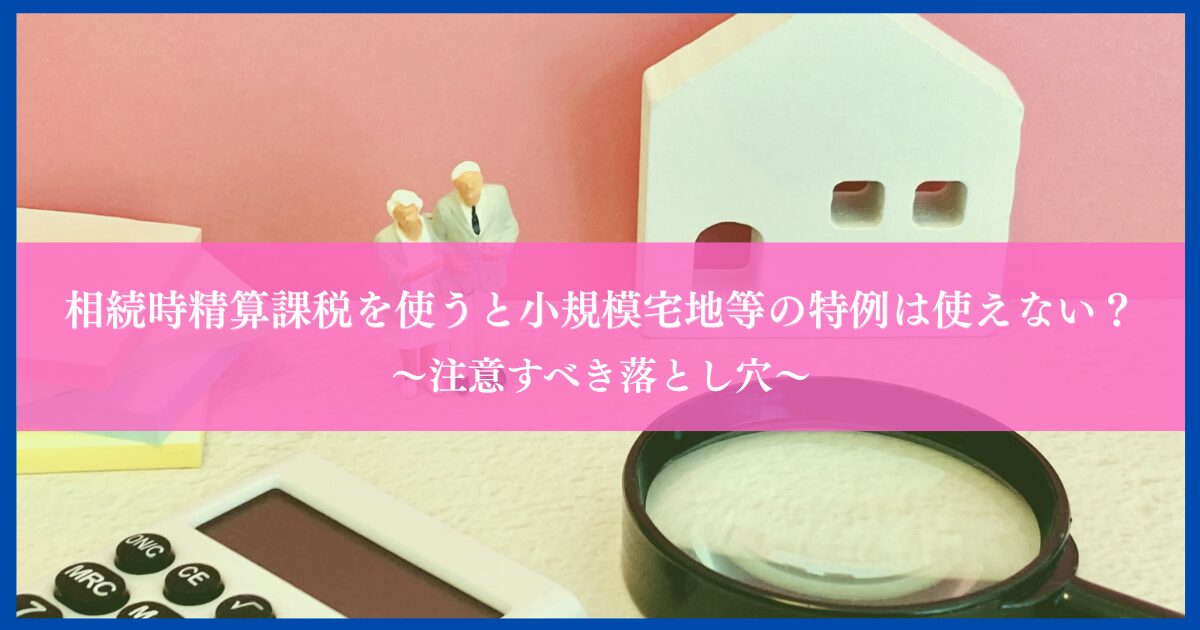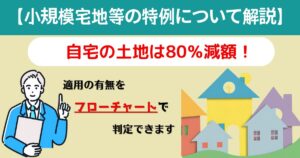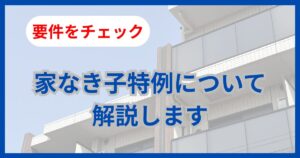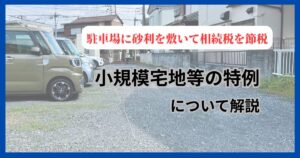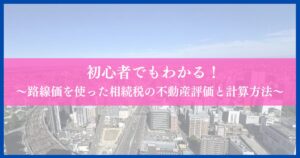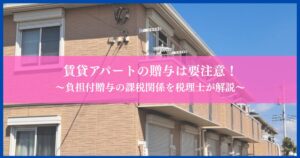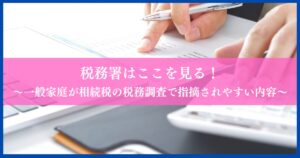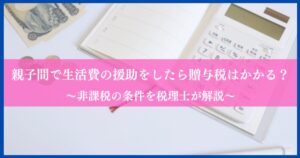「自分が生きているうちに早めに自宅を子どもに生前贈与しておこうか・・・」
そのように考えて、「相続時精算課税制度」を検討している人もいるのではないでしょうか。
しかし、その選択が将来の相続税を大幅に増加させることになる可能性があります。
なぜなら、自宅の生前贈与や相続を検討するときは「小規模宅地等の特例」についても考慮する必要があるためです。
「生前に自宅を贈与して、将来の相続税を軽減したい」
「親と同居している自宅を引き継いで住み続けたい」
そんな希望を持つ人ほど、相続時精算課税制度の利用には注意が必要です。
本記事では、相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例の仕組み、関係性、よくある誤解、失敗例をわかりやすく解説します。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続時精算課税とは
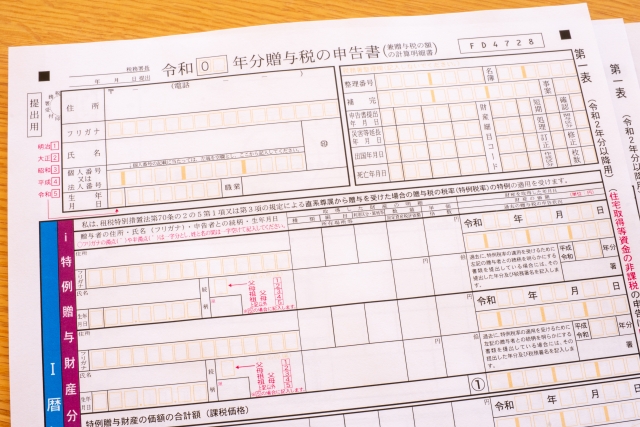
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫への生前贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度のことをいいます。
ただし、注意点として贈与税は非課税でも、相続が発生したときにその贈与財産を相続財産に加算して相続税を課税するという仕組みになっています。
相続時精算課税制度が創設された目的は高齢者の財産を早期に若年層に移転し、有効活用してもらうことにより経済を活性化させるという点です。
相続時精算課税を利用すれば、本来であれば相続発生時に子どもや孫に移転する財産を、贈与税がかからない形で早期に移転することができます。
相続時精算課税について詳しくは次の記事で解説しています。
小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは亡くなった人の自宅の土地を配偶者や同居している子どもなどが相続した場合、その土地の評価額を80%減額してくれる特例のことをいいます。
この特例により、本来は評価額が5,000万円の土地であっても1,000万円まで減額できることになります。
相続税の計算では土地の評価額が大きく影響するため、節税効果が非常に大きな特例です。
小規模宅地等の特例や土地の評価について詳しくは次の記事で解説しています。
相続時精算課税と小規模宅地等の特例は併用できない

結論からいいますと、相続時精算課税で贈与を受けた土地については、小規模宅地等の特例は適用できません。
小規模宅地等の特例はあくまでも亡くなった人から土地を「相続又は遺贈(遺言書により財産を貰うこと)」で取得した場合に限り適用できるためです。
相続時精算課税で贈与を受けた土地は相続開始前に所有権が移っているため、上記の要件を満たさなくなります。
「でも、相続時精算課税で贈与を受けた財産は相続税の計算に含まれるのだから、相続とみなされるのでは?」と疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
確かに、相続税の計算上は相続財産に含めて計算を行うことになります。
しかし、贈与で所有権が移っていることに変わりはないため、小規模宅地等の特例は使えないのです。
なお、「相続時精算課税で現金などの贈与は受けているが、土地は相続で取得する」といった場合は、問題なく小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
さらに、「自宅の建物は相続時精算課税で贈与を受けているが、土地は相続で取得する」という場合は、小規模宅地等の特例を受けられるケースと受けられないケースが存在します。
そのような場合は、税理士に事前に確認することをおすすめします。
相続税の負担が増えた失敗例

次のケースで自宅の土地と建物を相続時精算課税で贈与した場合と、贈与しなかった場合の相続税を計算してみます。
相続財産:自宅土地2,000万円、自宅建物500万円、預貯金2,500万円
相続人:子ども1人
土地の面積:200㎡
▼自宅の土地建物を相続時精算課税で贈与した場合の相続税
課税価格:2,000万円(自宅土地)+500万円(自宅建物)+2,500万円(預貯金)=5,000万円
課税遺産総額:5,000万円-3,600万円(基礎控除額)=1,400万円
相続税:1,400万円×15%-50万円=160万円
▼自宅の土地建物を相続時精算課税で贈与しなかった場合
課税価格:2,000万円(自宅土地)-1,600万円(小規模宅地等の特例による減額金額)+500万円(自宅建物)+2,500万円(預貯金)=3,400万円
課税遺産総額:3,400万円-3,600万円(基礎控除額)<0万円 ∴ 0万円
相続税:0万円
相続時精算課税で贈与をした場合、土地と建物の評価額の合計は2,500万円のため、贈与税は発生しません。
ですが、相続時精算課税で贈与を受けた財産に小規模宅地等の特例は使えないため、相続時に160万円の相続税が発生します。
反対に相続時精算課税で贈与をしておらず、自宅の土地建物を相続で取得した場合は、小規模宅地等の特例が使えるため、上記のケースでは相続税がかからない結果になりました。
このように、相続時精算課税で贈与をすると小規模宅地等の特例が使えないために相続税が増えてしまうといったことが起こりますので、慎重な判断が必要です。
おわりに
相続時精算課税は、2,500万円まで非課税で子や孫に自宅を生前贈与できるというメリットがあります。
その一方で相続時に小規模宅地等の特例が使えないというデメリットも存在します。
小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、節税効果の差は数百万円に及ぶこともあります。
制度の仕組みや関係性を正しく理解し、安易に生前贈与を進めるのではなく、相続全体を見据えたうえでの計画が必要です。
ご自身で考えてもわからないといった場合は、相続税に詳しい税理士など専門家の意見を求めることも必要になるでしょう。