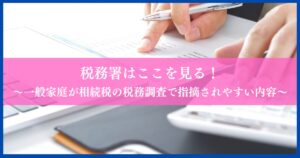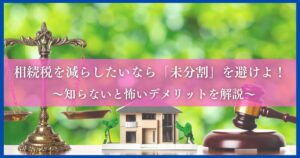近年、金の価格が高騰し、投資対象として購入する人が増えてきました。
もしも、亡くなった人が金を所有していた場合は、相続税の対象になります。

でも、金なんて現物で所有しているものだし、相続税の申告書に計上しなくても税務署にはバレないのではないでしょうか?



いいえ、税務署は様々な角度から財産を調査するため、隠そうとしても高確率で発覚してしまいます。
また、金を隠していたことが発覚した場合、大きなペナルティが発生する可能性があります。
本記事では相続時における金の評価方法や金を相続したことが税務署にバレる理由、相続後に金を売却したときの税金の取り扱いについて解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。
金の評価方法


亡くなった人が金を所有していた場合、相続税の対象になります。
金の相続税評価額は「亡くなった日の業者の買い取り価格」に基づいて計算します。
< 算式 >
業者の買い取り価格×g数
※使用するのは金取引業者の買い取り価格であって金取引業者が消費者に売却する際の小売価格ではありません。
買い取り価格は金取引業者に電話で確認するか、ホームページで確認しましょう。
金を相続した場合は上記の算式で計算した金額を相続税の申告書に計上する必要があります。



亡くなった人が購入した金額ではなく、亡くなった日の業者の買い取り価格で計算するのですね。
金を相続したことが税務署にバレる理由


相続した金を隠して相続税の申告をした場合、税務署にはバレるのでしょうか。
結論から言うと高確率でバレてしまいます。
税務署は主に次の3つの方法で相続人が金を相続したことを把握します。
(1)支払調書により把握
金を相続した相続人はその後、タイミングをみて金を金取引業者に売却するという流れになることが多いです。
金取引業者は一度に200万円以上の金の売買取引があった場合、その取引内容を記載した「支払調書」と呼ばれる書類を税務署に提出することが義務付けられています。
この支払調書により、税務署は相続人が金を相続したことを把握します。
支払調書に記載される内容は次のようなものです。



なるほど。
金を売却すると買い取り業者を通して税務署に情報が流れるのですね。
相続税の申告書に計上されていない金を相続人が売却したら非常に怪しまれそうですね・・・



その通りです!
(2)亡くなった人と相続人の預貯金の取引履歴から把握
税務署は相続税の申告があった場合、亡くなった人と相続人の預貯金の取引履歴を確認します。
金融機関に照会をかけて、最長過去10年分の取引履歴の調査を行います。
金取引業者との取引があるにもかかわらず、相続税の申告書に金が計上されていない場合、税務調査に選ばれる確率も上がってしまいます。
その際に追及されて金を隠していることがばれてしまう可能性が高いでしょう。
金を家のどこかに隠せばバレないだろうという考えは非常に危険です。
税務署は預貯金の取引履歴から相続人が金を相続したことを把握します。



亡くなった人が金取引業者に多額の振り込みを行っているにもかかわらず、相続税の申告書に金が計上されていない場合、税務調査に行ってみようとなるわけです。



確かにそういった状況だと税務調査が来てもおかしくはないですね。
(3)金取引業者への照会で把握
金にはシリアルナンバーが刻印されているため税務署が金取引業者へ照会をすると金を所有していることが発覚します。
支払調書や預貯金の取引履歴を見て、怪しいと思われた場合には徹底的に調査されてしまいます。
金の相続や売買は申告漏れが多いため税務署は様々な角度からその実態を把握できるように仕組みを作っています。
現在はバレずに隠し通すことは不可能なため金を相続した場合は適切に申告を行いましょう。
金を隠したことが税務署にバレた場合のペナルティ
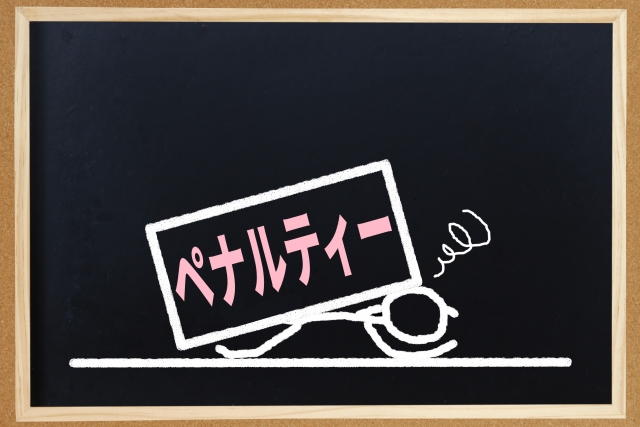
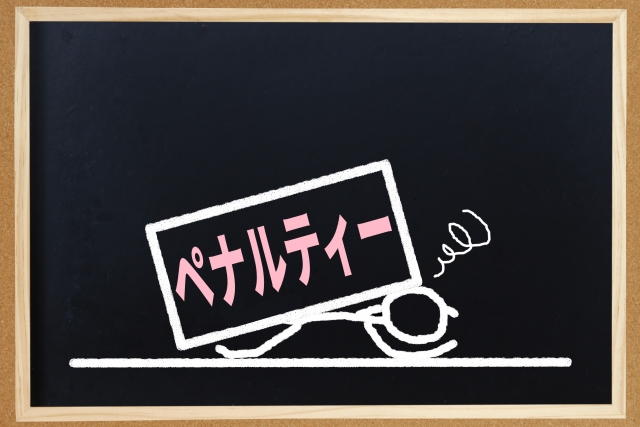
金を隠して相続税の申告を行った場合やそもそも相続税の申告をしなかった場合、次の税金がペナルティとして課されます。
(1)延滞税
(2)過少申告加算税
(3)無申告加算税
(4)重加算税
それぞれがどのような税金なのかについて順番に解説していきます。
(1)延滞税
延滞税は相続税の納付が納期限(亡くなった日の翌日から10か月)に間に合わなかった場合に、遅れた日数に応じて課税されます。
具体的には次のようなケースです。
延滞税の税率は次の通りです。(令和6年に適用される税率)
納期限の翌日から2か月を経過する日まで 2.4%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後 8.7%
(2)過少申告加算税
過少申告加算税は相続税の期限内申告を行った後に、本来納めるべき税額よりも納付した税額が少ないことが判明し、修正申告を行った場合に課税されます。
過少申告加算税の税率は追加で納付することになった相続税(本税)の10%※です。
※修正申告を行うタイミングや税額によって税率が5%や15%になる場合があります。
正当な理由がある場合や税務調査の通知が来る前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税は課税されません。
(3)無申告加算税
無申告加算税は相続税の期限後申告をした場合や、相続税の申告をしていない状態で税額の決定処分を受けた場合に課税されます。
無申告加算税の税率は納付すべき相続税(本税)の15%※です。
ただし、50万円を超え300万円以下の部分は20%※、300万円を超える部分は30%になります。
※申告を行うタイミングや税額によって税率が5%、10%、15%、25%になる場合があります。
正当な理由がある場合や申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告・納付を行った場合には無申告加算税は課税されません。
(4)重加算税
重加算税とは財産隠しや書類偽装を行うなど悪質な行為が確認された場合に過少申告加算税や重加算税に代えて課税されます。
重加算税の税率は過少申告の場合、新たに納めることとなった相続税(本税)の35%、無申告の場合は納付すべき相続税(本税)の40%です。
相続した金を隠して相続税申告を行い、後になってその事実が発覚した場合は上記の税金がペナルティとして発生します。



こんなにたくさんペナルティが発生してしまうのなら始めから
ちゃんと申告したほうが良さそうですね。



そうですね。
そもそも金を隠して相続税の申告を行うことは脱税に該当しますので、適切に申告を行いましょう。
金を売却した時の税金


相続した金を売却したときは売却益に対して所得税がかかります。
この売却益のことを譲渡所得といいます。
金を売却したことによる譲渡所得は給与所得など他の所得と合算され、合算後の金額に所得税率を乗じて所得税を計算することになります。
所得税は所得が高くなるにつれて税率も高くなる超過累進税率が採用されているため金を売却したことに伴う譲渡所得が高くなれば高くなるほど所得税の負担も大きくなります。



相続した時は相続税がかかって、売却した時は所得税がかかるのですね・・・



そうですね・・・
では、譲渡所得はどのように計算するか確認しましょう。
金の所有期間が5年以内の場合 (短期譲渡所得)
売却金額-(取得費+譲渡費用)=売却益
売却益-50万円(特別控除額)=短期譲渡所得
金の所有期間が5年を超える場合 (長期譲渡所得)
売却金額-(取得費+譲渡費用)=売却益
{売却益-50万円(特別控除額)}×1/2=長期譲渡所得
相続で金を取得した場合の取得費は亡くなった人が購入した金額を引き継ぎます。
なお、取得費が不明な場合は売却金額の5%相当額を取得費とみなして計算します。
また、所有期間については亡くなった人が金を購入したときから、相続人が相続後に金を売却するときまでの期間でカウントします。



所有期間によって計算方法が違うのですね!



売却益から50万円を控除するところまでは一緒ですが、所有期間が5年超の場合、そこからさらに2分の1の金額にします。
具体例
1000万円-(600万円+50万円)=350万円(売却益)
(350万円-50万円)×1/2=150万円(長期譲渡所得)
所有期間は亡くなった人が購入してから相続人が売却するまでの期間(6年)でカウントするため、長期譲渡所得に該当します。
所得税を節税できる金の売却方法





譲渡所得の計算方法はわかりました。
所得税を節税できる金の売却方法はないのでしょうか?



良いご質問ですね。
実は所得税を節税できる金の売却方法が3つあります。



ぜひ、教えてください!
(1)相続人複数人で相続して売却する
相続財産に金地金や金の延べ棒が複数あり、相続後に売却することが確定している場合、相続人複数人で相続してそれぞれ別々に売却しましょう。
既に解説した通り、所得税は所得が高くなるにつれて税率も高くなる超過累進税率が採用されています。
1人の相続人がまとめて金を相続してまとめて売却した場合、金の譲渡所得によりその相続人の合計所得が大きくなり、所得税の負担も大きくなります。
所得税を節税したい場合は遺産分割協議で金を複数の相続人で相続してそれぞれ別々に売却しましょう。


(2)複数年に分けて売却する
所得税は1月1日~12月31日の所得に基づいて計算されます。
そのため、相続した金のうち、一部を年内に売却し、年が明けてまた一部を売却すればそれぞれ別の年の所得になります。
このように複数年に分けて金を売却することで所得税の負担を少なくできる可能性があります。
ただし、売却時期を分けるということは金の価格変動のリスクを負うことになりますので、その点は注意しましょう。


(3)相続税額の取得費加算の特例を適用する
相続した金に対して相続税が課税された場合、その相続税を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる特例があります。
この特例を「相続税額の取得費加算の特例」といいます。
相続した金を売却した場合、この特例を使うことで譲渡所得が抑えられ、所得税を節税できます。
なお、この特例は相続した金を相続開始の日から3年10か月以内に売却しないと適用できないため注意が必要です。
具体例
1000万円-(600万円+50万円+100万円)=250万円(売却益)
(250万円-50万円)×1/2=100万円(長期譲渡所得)



工夫して金を売却すれば所得税を節税できそうですね!



金の売却まで見越して遺産分割を行うなど注意が必要になりますが節税は可能です。
まとめ
本記事では相続時における金の評価方法や金を相続したことが税務署にバレる理由、相続後に金を売却したときの税金の取り扱いについて解説しました。
相続した金を隠したら高確率で税務署にバレてしまいます。
また、ペナルティの税金も非常に大きなものになります。
相続税の申告は適切に行いましょう。