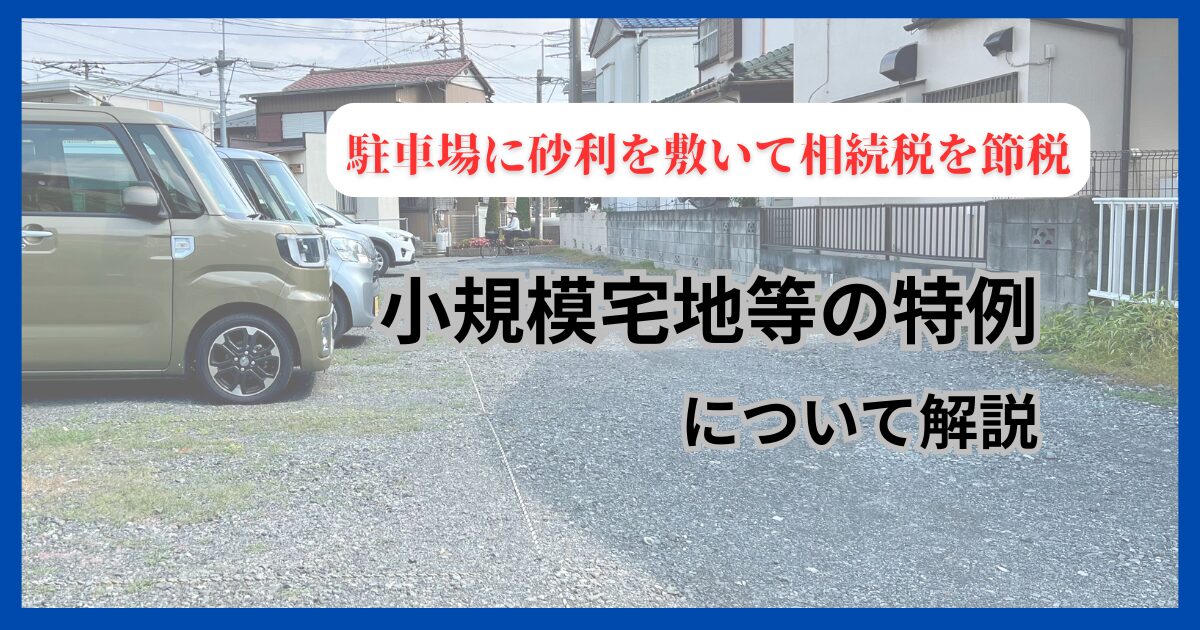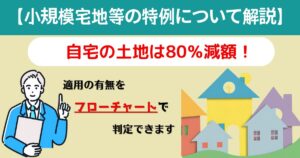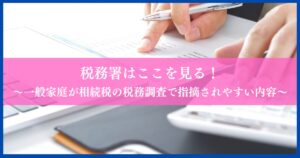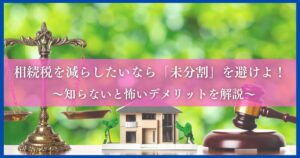小規模宅地等の特例は亡くなった人の居住用の土地のほか、貸付事業用の土地についても適用できます。
貸付事業用の土地とは賃貸アパートが建っている土地や貸駐車場の土地のことをいいます。
基本的には建物が建っている土地でないと小規模宅地等の特例を適用することはできませんが、砂利敷きの駐車場であれば小規模宅地等の特例を適用できます。
本記事では砂利敷きの駐車場に小規模宅地等の特例を適用するための要件などについて解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
貸付事業用宅地等とは

(1)貸付事業用宅地等とは
貸付事業用宅地等とは亡くなった人が相続開始の直前において、貸付事業のために使用していた土地のことをいいます。
そして貸付事業用宅地等は小規模宅地等の特例の対象になります。
小規模宅地等の特例というと、自宅の土地のイメージが大きいですが、貸付用の土地についても特例を適用できます。
貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用した場合、その土地のうち200㎡までの部分について評価額を50%減額することが可能です。
なお、居住用宅地の小規模宅地等の特例については次の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
(2)貸付事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用するための要件
続いて貸付事業用宅地等について小規模宅地等の特例を適用するための要件について見ていきます。
①相続税の申告期限までに貸付事業を継続していること
相続税の申告期限までに貸付事業を継続している必要があります。
申告期限までに貸付事業を廃業してしまうと小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
②相続税の申告期限までに土地を保有していること
相続税の申告期限までに土地を保有している必要があります。
申告期限までに売却してしまわないように注意しましょう。
③相続開始前3年以内に貸付を開始した土地ではないこと
相続開始前3年以内に貸付事業を始めた場合、小規模宅地等の特例の適用は受けることができません。
相続税の節税のためだけに貸付事業を始めたものと捉えられてしまうためです。
ただし、以前より複数の土地について貸付事業をおこなっていて、相続開始前3年以内に新たに貸付事業として使い始めた土地については問題なく小規模宅地等の特例を適用できます。
④土地が建物又は構築物の敷地として使われていること
土地の上に建物か構築物がある場合のみ、小規模宅地等の特例は適用できます。
したがって、青空駐車場などについては小規模宅地等の特例を適用できません。
⑤相続税の申告を行うこと
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには相続税の申告を必ず行う必要があります。
特例を適用して計算した相続税が0円になったとしても申告をしましょう。
原則:砂利敷きの駐車場は小規模宅地等の特例を適用できる

砂利敷きの駐車場は原則として貸付事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できます。
先ほど貸付事業用宅地等の要件の1つに、「土地が建物又は構築物の敷地として使われていること」という点について解説しました。
そして砂利は構築物に該当します。(減価償却資産の耐用年数に関する省令より)
つまり、駐車場を経営している人は駐車場に砂利を敷いておくだけで小規模宅地等の特例を適用でき、相続税の節税に繋がる可能性があります。
例外:砂利敷きの駐車場に小規模宅地等の特例を適用できない場合もある

砂利敷きの駐車場は原則として貸付事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用できると解説しました。
しかし、例外的に小規模宅地等の特例を適用できない場合がありますので注意が必要です。
小規模宅地等の特例を適用できない場合は次のような場合です。
(1)砂利のほとんどが地面に埋もれている場合
砂利のほとんどが地面に埋もれている場合は小規模宅地等の特例を適用できない可能性が高いです。
例えば何十年も前に砂利を敷設していて、相続時にはそのほとんどが地中に埋没して土が剥き出しの状態になっている場合などです。
このような場合は構築物の敷地として使われている土地であるとは言えません。
砂利が埋もれてきている場合は常時補充してびっしりと敷き詰めておく必要があります。

(2)貸付事業のために購入した砂利ではなくもともと石がたくさんある土地の場合
もともと石がたくさんある土地についても小規模宅地等の特例を適用できない可能性が高いです。
小規模宅地等の特例を適用するには、駐車場業を始めるにあたり、自らが購入した構築物である砂利を敷き詰めておく必要があります。
(3)近隣相場よりも大幅に低い金額で貸している場合
砂利敷きの駐車場であったとしても、近隣相場よりも大幅に低い金額で貸している場合も小規模宅地等の特例を適用できない可能性があります。
小規模宅地等の特例を適用するには駐車場業として「相当の対価」で貸付を行っている必要があります。
「相当の対価」とはいくらなのかという点について明確な決まりがあるわけではありませんが、以下のような観点から総合的に判断します。
近隣相場と同程度の賃料で貸付を行っている場合は相当の対価で貸付を行っていると考えられます。
賃料から固定資産税などの経費を差し引いて利益が出ているようであれば相当の対価で貸付を行っていると考えられます。
上記①、②の両方かいずれかを満たしていれば小規模宅地等の特例の適用はできると考えて問題ないでしょう。
貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例の計算例

小規模宅地等の特例を適用すると貸付事業用宅地等のうち200㎡を限度面積として評価額が50%減額になります。
計算例を使って確認していきます。
(1)貸付事業用宅地等の面積が200㎡以内のケース
→土地の面積が200㎡以内のため土地のすべてに小規模宅地等の特例を適用できます。
①5,000万円×50%=2,500万円(小規模宅地等の特例による減額金額)
②5,000万円-2,500万円=2,500万円(相続税評価額)
(2)貸付事業用宅地等の面積が200㎡を超えるケース
→土地の面積が限度面積200㎡を超えるため土地のうち200㎡部分について小規模宅地等の特例を適用できます。
①5,000万円×(200㎡÷400㎡)=2,500万円(小規模宅地等の特例が適用される面積部分の評価額)
②2,500万円×50%=1,250万円(小規模宅地等の特例による減額金額)
③5,000万円-1,250万円=3,750万円(相続税評価額)
小規模宅地等の特例の適用を受けるための添付書類

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには相続税の申告書に次の書類を添付する必要があります。
・マイナンバーカードの写し(表面・裏面)
・亡くなった人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図
・遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
・以前より貸付事業を行っていて、相続開始前3年以内に新たに貸し付けを始めた土地について特例を使う場合は確定申告書や賃貸借契約書の写し
駐車場にかかる小規模宅地等の特例についてよくある質問
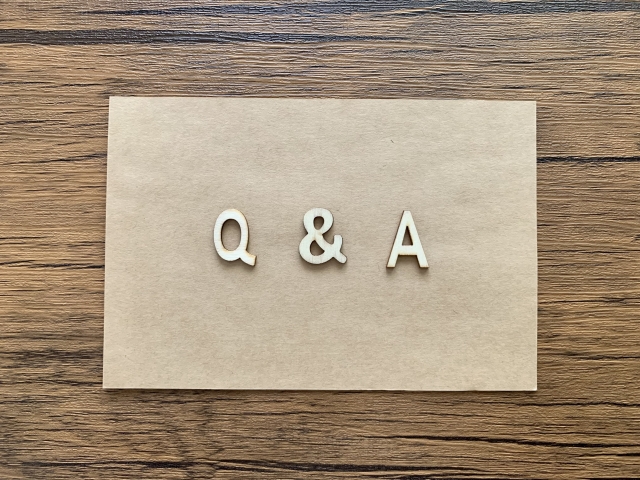
(1)駐車場の賃料収入について確定申告をしていなかった場合はどうなりますか?
小規模宅地等の特例に「所得税の確定申告を行っていること」という要件はありません。
したがって確定申告をしていなかったとしてもその他の要件を満たすのであれば小規模宅地等の特例は適用できます。
しかし、それをきっかけとして確定申告をしていなかったことについて税務署から指摘される可能性がありますので、過年度分も含めて確定申告をする必要があるでしょう。
(2)相続開始後に急いで砂利を敷けば小規模宅地等の特例を適用できますか?
相続開始後に砂利を敷いても小規模宅地等の特例を適用することはできません。
相続開始時点において構築物の敷地として使われている必要があります。
税務署がグーグルマップ等で過去の写真を確認したらすぐにバレることなので相続後に砂利を敷いて、小規模宅地等の特例を適用して申告するのは絶対にやめましょう。
そのような行為は脱税行為とみなされる可能性があります。
(3)駐車場の一部には砂利が敷き詰めてありますが、他の部分は土が剝き出しです。この場合はどうなりますか?
砂利が敷き詰めてある部分の面積を測ってその部分にのみ小規模宅地等の特例を適用することができます。
ただし、土地の面積に対して砂利が敷いてある部分の面積が明らかに小さすぎる場合は、特例を税務署から否認される可能性があります。
なお、土が剥き出しの部分には間違いなく小規模宅地等の特例は適用できません。
(4)砂利は敷いてありませんが、車止めやロープはあります。小規模宅地等の特例を適用できますか?
車止めやロープは構築物には該当しません。
したがって小規模宅地等の特例を適用することはできません。
(5)アスファルト舗装がされている場合、小規模宅地等の特例を適用できますか?
アスファルトも構築物に該当するため、小規模宅地等の特例を適用できます。
まとめ
本記事では砂利敷きの駐車場に小規模宅地等の特例を適用するための要件などについて解説しました。
本記事で解説したこと以外にも、居住用宅地との併用計算など注意すべき点が多数あります。
小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告を行う場合は税理士に相談することをおすすめします。