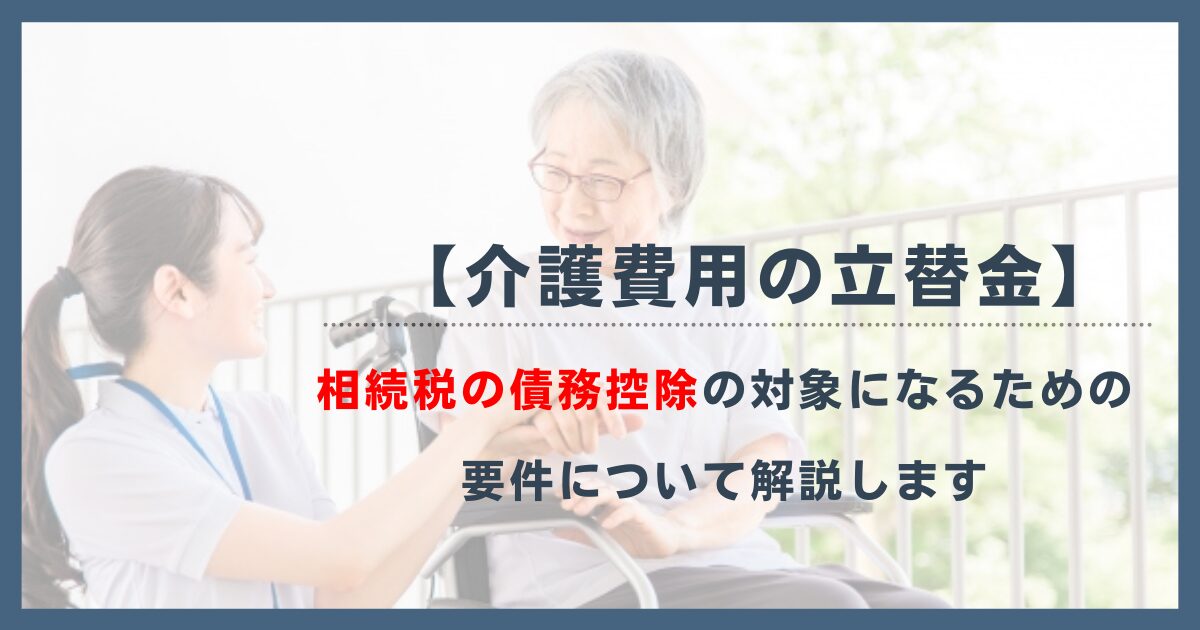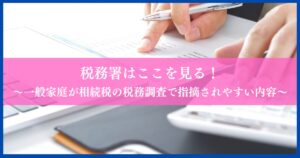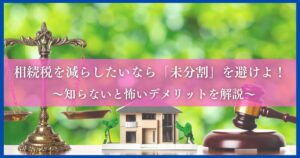親が亡くなり、これから相続税の申告を行う予定です。
私は数年前から親の介護費用を立て替えていたのですが、この立替金は相続税の計算上、何かしら考慮して貰えるのでしょうか?



亡くなった人の介護費用を親族が立て替えていた場合、相続税の計算において「債務控除」できる可能性があります。
今回は親族が立て替えていた介護費用が、債務控除の対象になるための要件について解説していきます。
近年の高齢化社会に伴い、高齢者の介護費用も増加傾向にあります。
そのような状況もあり、親の介護費用を立て替えていた相続人も多いのではないでしょうか。
本記事では、親族が立て替えていた介護費用が相続税の計算上、債務控除の対象になるための要件について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。


ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表
東北税理士会 仙台北支部所属
税理士 高橋 祥太
これまで多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。
相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続税の債務控除とは
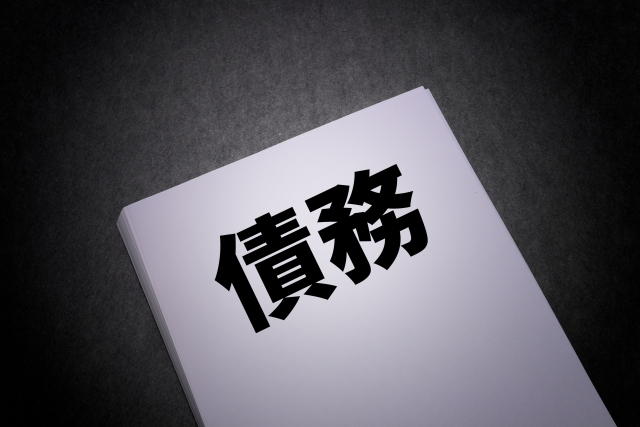
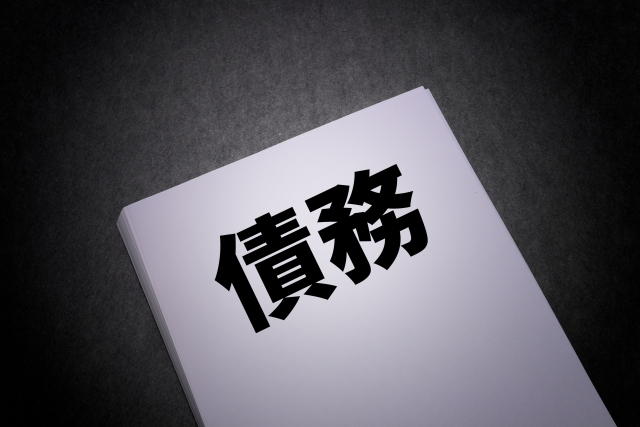
相続税の債務控除とは、亡くなった人が残した債務を遺産総額から控除できる制度のことをいいます。
債務には次のようなものが該当します。
・金融機関、親族などからの借入金
・亡くなった後に支払う所得税・住民税・固定資産税などの税金
・亡くなった後に支払う医療費
・亡くなった後に支払う公共料金 など
そして親族が亡くなった人の介護費用を立て替えていた場合、亡くなった人から見れば、自分で支払うべき費用を親族に負担して貰っていた状態になります。
つまり、「親族に対する未払金」として債務控除の対象になる可能性があります。



立て替えてもらっていたお金は親族に対する債務と考えるのですね!



その通りです!
ただし、介護費用を立て替えていたとしても必ずしも債務控除の対象になるとは限りませんので注意が必要です。
介護費用の立替金が相続税の債務控除として認められるための要件





続いて介護費用の立替金が債務控除として認められるための要件について解説していきます。
次の要件のすべてを満たすようであれば、債務控除の対象になります。
(1)扶養義務の履行に該当しないこと
介護費用を立て替えていたことが、「扶養義務の履行」に該当する場合は債務控除の対象になりません。
扶養義務の履行とは、民法で定められた扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹)が、扶養権利者(扶養を受ける権利がある経済的に自立ができない人)を経済的に援助することをいいます。
そのため、介護費用の支払いが扶養義務の履行にすぎない場合は、立替金として債務控除をすることはできません。
介護費用の支払いが扶養義務の履行に該当しない場合は、わかりやすく説明すると次の通りです。
親に経済的な余力がある(自身のお金で支払おうと思えば介護費用を支払える)状態であったが、子が介護費用を立て替えていた場合
上記のような場合であれば扶養義務の履行に該当しないと考えられます。
一般的に、相続税が発生するくらいの財産がある場合は、親に経済的余力があると判断して問題ないでしょう。
(2)立替の事実が把握できること
立て替えたお金がいくらあったかを把握できるようにしておく必要があります。
領収書を保管しておき、領収書がない場合はノートなどにメモ書きを残しておきましょう。
なお、親の口座からお金を引き出し、そのお金で介護費用の支払いをした場合は立替金には該当しません。
親の口座からお金を引き出して支払ったものと相続人のお金から支払ったものが混在している場合は、介護費用の原資についても後から見てわかるようにしておきましょう。
(3)誰が立替をしたかわかるようにしておくこと
(2)と似たような話ですが、介護費用を立て替えた人が誰かわかるようにしておく必要があります。
立て替えた人がわからないと、亡くなった人から見て誰に対する債務なのかがわからなくなってしまい、債務控除ができなくなる可能性があります。



面倒でも、領収書を保管し、ノートにメモ書きを残しておくことが重要になるのですね!



その通りです!
上記の要件をすべて満たせば立て替えた介護費用について債務控除が可能です。
ただし、扶養義務の履行に該当しないかどうかなど、判断が難しい場合もありますので税理士に相談することをお勧めします。
何年前までの介護費用の立替金について債務控除が可能か





介護費用の立替金が債務控除として認められるための要件についてはわかりました。
ところで亡くなる何年前までの立替金について、債務控除できるのでしょうか?



良いご質問ですね。
では、何年前までの立替金について債務控除できるか解説していきます。
民法上、債務は次のいずれか早い時点を経過することで、時効により消滅します。
・債権者が権利を行使できることを知った時から5年
・債権者が権利を行使できる時から10年
ただし、時効期間が経過しても、自動的に債務が消滅するわけではありません。
債務が消滅するためには、債務者が時効を主張する時効援用の手続きを行う必要があります。
税法において「何年前までの立替金については債務控除できる」といったことが定められているわけではありません。
亡くなった人が時効援用の手続きをしていなかった場合は、親族に対する債務が残っていたと考えて、介護費用の立替金は債務控除の対象になります。
亡くなった人が時効援用をしていなければ何年前の立替金であっても債務控除が可能



一般的に親が子に立て替えてもらっている介護費用について、時効援用の手続きを行うことはないと考えられます。
そのため前の章で解説した、債務控除として認められるための要件を満たすのであれば、何年前の立替金であっても債務控除することができます。
まとめ
本記事では親族が立て替えていた介護費用が、債務控除の対象になるための要件について解説しました。
・扶養義務の履行に該当しないこと
・立替の事実が把握できること
・誰が立替をしたかわかるようにしておくこと
上記の条件を満たせば、債務控除が可能です。
ただし、扶養義務の履行に該当しないかどうかは、個別に判断が必要になってくる部分でもあります。
判断に迷った場合は税理士に相談して適正に相続税申告を行いましょう。